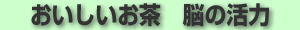
渋み→老化を防止
うまみ→安らぎ効果
| もうすぐ新茶が出回り、お茶のおいしい季節がやってくる。このうまみを演出するのがテアニンと呼ぶ成分だ。最近の研究で脳をリラックスした状態にする力が潜んでいることが判明。体にいい飲み物として人気のお茶に、また1つ新たな健康パワーが加わる。 |
テアニンはたんぱく質を構成しているアミノ酸の一種。湯を注ぐ前の茶葉には、1−2%のアミノ酸が含まれているが、そのうちおよそ半分を占める。うまみ成分として有名なアミノ酸であるグルタミン酸と化学構造がよく似ている。
静岡県立大学の横越英彦教授の研究グループは、まず、ラットを使った実験でテアニンが脳に働きかけていることを突き止めた。テアニンをラットの脳に直接ふりかけると、かけた量に比例するかたちでドーパミンと呼ぶ記憶や学習にかかわっている物質の分泌量が増えた。
次にボランティア50人を募り、人間の脳に与える影響を調べた。50−200ミリグラムのテアニンが入った水を飲んでもらい、脳波を10分おきに測定した。約40分後、個人差はあるが脳がリラックスしている状態を示すα波がほぼ全員で強く出るようになっていた。
横越教授によると「人間の脳は、リラックスした状態で本来の力を最大限発揮できる」。たとえば仕事や勉強で集中力を必要とする場合、「40分前に湯飲みで5杯から10杯を目安に飲むと効果的」という。
お茶のもう1つの成分、カテキンにも脳を元気にするパワーがありそうだ。カテキンは渋みのもとになる物質で、ワインやチョコレートに含まれるポリフェノールの仲間。発がんの原因になるといわれている活性酸素の活動を抑え込み、細菌やウイルスをやっつける強い抗酸化力が知られている。
静岡県立大の海野けい子助手らは、0.02%のカテキンを含む水を、1日あたり5−13ミリリットルマウスに飲ませた。カテキンを混ぜないふつうの水を飲ませたマウスと比較すると、危険を回避するための方法を習得する時間が短くてすみ、学習能力が向上していることを確認した。老化によって起きる脳の萎縮も抑えられた。
この動物実験で使用したカテキン量は、人間にあてはめると1.8リットル−3リットルのお茶を飲む計算になる。1日で飲むとなるとかなりの量だが、「2日間かけて飲んでも効果は薄れないだろう」(海野助手)。毎日、一定量のお茶を飲む習慣をつければ、脳の老化を予防する効果が期待できそうだ。
海外でも米研究グループが、カテキンの抗酸化作用がアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患の予防にも役立つ可能性を指摘した論文を発表するなど、「ジャパニーズ・ティー」への関心は高い。
ペットボトル入りのお茶もいいが、やはり急須で入れ、ゆったりとした気分で飲みたいもの。テアニンやカテキンを上手に摂取できるお茶の入れ方のコツを紹介しよう。
実はテアニンは、一定の時間太陽光にあたるとカテキンに変化する。このため、光をさえぎった状態で育てる玉露などの高級茶葉や抹茶、せん茶でも日に当たる期間が比較的短い新茶に多い。玉露の場合で100グラムに約2.7グラム、抹茶だと2.3グラム、新茶(せん茶)には約2グラムのテアニンが含まれているものもあるという。
テアニンは約60度、カテキンは約80度の湯で溶け出しやすい。お茶を入れる時には、カルキ臭を抜くため水をいったん沸騰させてからさまして使うのが基本。より多くのテアニンを抽出したいのであれば、さます時間を長めにとり、ぬるま湯でお茶を入れるのがよい。
ペットボトルに新カテキン 抗酸化力が2倍
手軽さと健康ブームでペットボトル飲料の緑茶が大人気だが、急須で入れたお茶と同じ効果を期待してもいいのだろうか。
共立薬科大学の金沢秀子教授は、市販されている15種類のペットボトル入り緑茶カテキンについて調べた。急須でお茶をいれる場合に比べ量は少なかったが、その代わりに分子構造が変化した別のカテキンが見つかった。
この新カテキンの抗酸化力は、従来のカテキンよりも2倍以上にもなるという。脂肪の代謝を促進する作用も強い可能性があることもわかった。
研究では大半のペットボトル入り緑茶が95度の熱湯で30分かけてゆっくりと煮出したお茶と同じ状態であることもわかった。メーカー各社は製法の詳細を明らかにしていないが、「かなり高温の加熱処理で新カテキンができた可能性がある」(金沢教授)という。
| ・カテキンの一種「ガレート型カテキン」に血液中のコレステロールを下げる作用 |
| ・少人数の研究だが、C型肝炎の治療効果を高める作用 |
| ・肺がんなどのがん予防効果 |
| ・細菌やウイルス感染の制御、花粉症の症状を抑えるなど、アレルギーや免疫に効く |
| ・月経前の不調(月経前症候群)をテアニンが和らげる |
《ホームページ》
◆お茶の作り方やシュリ、効能について詳しく知るなら
伊藤園の「お茶百科」(http://www.itoen.co.jp/tea/index.html)
◆お茶のセミナーやシンポジウムなどの情報は
世界緑茶協会(http://www.o-cha.net/) |
|
|
|
![]()
![]()

![]()
![]()
