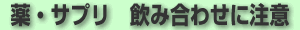
薬効弱めたり副作用も
健康によいとサプリメントを愛用する人は多い。普段の食生活で不足がちになる栄養素を手軽に補うのには便利だが、病気で薬を服用している人は飲み合わせに気をつけたい。相性が悪いと薬の効果が弱まったり、思わぬ副作用を招いたりする危険がある。
2千年以上も昔からいくつもの薬効が知られてきた西洋オトギリソウ。別名セントジョーンズワートと呼ぶこのハーブ(薬草)は、気分がそう快になるという理由で欧米では人気が高い。国内でも濃縮エキスがサプリメントとして出回るようになった。軽いうつ症だと、抗うつ剤とほぼ同じような効果が期待できるとされており、副作用も少ない。
ただ専門家の間では、解毒酵素を増やして薬物の分解をすることが知られている。強心薬や抗てんかん薬、抗不整脈薬、免疫抑制剤と併用すると、薬が効かなくなることもある。薬の効果は血液中の濃度が一定割合を超えて初めて表れるが、その前に分解・排出されてしまい血中濃度を下げてしまうからだ。
抗うつ剤と併用すると作用が重複、脳内のセロトニンの働きが強まる。発熱やふるえ、意識障害といった症状がでる「セロトニン症候群」を引き起こすこともあるので、細心の注意が必要になる。
痴ほう症の改善や記憶力をよくする効果があるとされるイチョウ葉。血流を改善し、脳内に血液を多く供給する働きで脳こうそく予防にも役立つとされる。抗血小板作用と呼ぶ血が固まるのを妨げる働きもあるため、血栓防止薬と併用すると、傷口などから血が止まりにくくなることもある。イチョウ葉は、欧州各国では医薬品として使用されるという。
薬を飲むときの水にも気をつけたい。コップ1杯の水かぬるま湯が最善だが、最近は様々なミネラルウオーターが売られている。「カルシウムやマグネシウム成分を多く含むものは、薬の吸収に影響が出るため要注意」(東京大学付属病院薬剤部)だ。
北陸大学薬学部では、179種類のサプリメント(特定保健用健康食品66種、栄養機能食品18種、健康食品95種)を対象に、薬との飲み合わせを調べた。処方薬との相互作用が83パターン、市販薬との相互作用が44パターンあったという。
薬同士の相性問題とちがって、サプリメントとの飲み合わせに詳しい医師や薬剤師はまだ少ないのが現実。「先生、併用しても構わないですかと相談されても正直困る」(ある大学病院の医師)というのが医療現場の本音でもある。
サプリメント大手のファンケルは、春から飲み合わせに関する利用者の質問に対応する電話サービス(○電045・895・2288)を始めた。同社販売のサプリメント約100品目と市販薬も含む医薬品約3万2千品目との飲み合わせをデータベース化し、薬の効き目がどのように変化し、どの程度時間をあければ問題ないかなどををアドバイスする。
「月平均1千件の問い合わせがある」(同社学術本部の岡村博貴本部長)という。
あまり神経質になることもないが、北陸大薬学部の大嶋耐之助教授は「サプリメントは健康な人が健康維持のために飲むもの。このことを忘れないで」と話す。トラブルを防ぐために、愛用しているサプリメントの特性を確認してみよう。
▼サプリメント
血圧やコレステロール値を正常に保つことを助ける効果が科学的に証明されている「特定保健用食品」、ビタミンなど国が定めた規格基準に合致していて栄養成分を表示してよい「栄養機能食品」、そのほかの「健康食品」の3つに分類される。
米国では「栄養素を一種類以上含む栄養補給のための製品」として、法律で医薬品と食品の中間的な存在であると明確に位置づけている。
|
サプリメント
|
医薬品
|
相互作用
|
| ビタミンA |
血液凝固防止薬 |
抗血液凝固作用を増大 |
| 角化症治療薬 |
ビタミンA過剰症(頭痛や吐き気)と似た副作用 |
| ビタミンB6 |
パーキンソン病治療薬 |
薬の代謝を促進し効き目が弱くなる |
| ビタミンC |
利尿薬 |
Cを大量に摂取すると腎・尿路結石の可能性 |
| ビタミンE |
血液凝固防止薬 |
Eの大量摂取で出血傾向が強くなる可能性 |
| 葉酸 |
抗てんかん薬 |
薬の効き目が弱くなる |
| カルシウムやマグネシウムなど |
骨粗しょう症治療薬 |
薬と結合し腸管からの吸収を阻害。30分以上間隔をあける必要 |
| 西洋オトギリソウ |
抗てんかん薬、強心薬、抗不整脈薬、免疫抑制剤 |
医薬品の代謝が促進され血中濃度が低下する恐れ |
| イチョウ葉エキス |
血液凝固防止薬、解熱鎮痛剤 |
抗血小板作用があり、併用で出血傾向が強まる可能性 |
| カンゾウ(甘草) |
強心薬、利尿薬 |
カンゾウでカリウムの腎排泄が促進、低カリウム血症が起こり薬の作用が増強 |
| クロレラ |
血液凝固防止薬 |
ビタミンKを含むため、薬の効き目が弱まる |
| 青汁(ケール) |
血液凝固防止薬 |
ビタミンKを含むため、薬の効き目が弱まる |
(注)愛知、岐阜、静岡、三重4県の薬剤師会がまとめた「医薬品と健康食品の相互作用」をもとに作成
≪ホームページ≫
◆薬とサプリメントの飲み合わせを知るなら
東海4県情報システム委員会TOP/NET(http://www.topnet.gr.jp)
≪書籍≫
◆サプリメントを詳しく知るなら
『医療従事者のための機能性食品ガイド』(吉川敏一・辻智子編集、講談社) |
|
|
![]()
![]()

![]()
![]()
